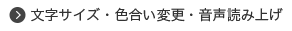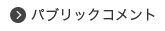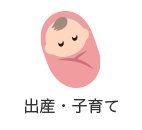トップ
> 医療費が高額になるとき
医療費が高額になるとき
国保の担当窓口に申請すれば、かかった医療費の一部をあとで払い戻してもらったり、現金の支給を受けられるものがあります。
ただし、法律の規定によって国保税の未納額がある場合は、これらの給付が受けられないこともありますのでご注意ください。
高額療養費
1か月(1日から月末まで)にかかった医療費(保険診療分)が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。下記の算出方法により、世帯の限度額を超えた場合には、診療月の2か月後下旬ごろに国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)をお送りします。
申請の手順
- 下記の算出方法により、世帯の限度額を超えた場合には、通常、診療月の2か月後の下旬に高額療養費に該当した人の世帯主あてに、申請書兼請求書が郵送されます。
- 申請書兼請求書に必要事項を記入して、返送または窓口に提出してください。
申請書兼請求書の記入箇所《 申請書兼請求書記入例(pdf 887 KB)》
申請書兼請求書記入例(pdf 887 KB)》
「日付」、「個人番号(任意)」、「氏名(印字されていますが、署名も必要です)」、「電話番号」、中断(8)の「発症又は負傷の理由」、「振込先口座(印字されている場合は確認のみ)」を記入してください。※振込先口座は世帯主名義のもの、他者の名義の場合は、世帯主直筆の委任状の添付または申請書一番下の欄に世帯主直筆の署名が必要です。
一部負担金の算出方法
●70歳未満の人の場合同一月内の医療機関、入院、外来、診療科ごとの保険診療自己負担額。だたし、21,000円を超えたものが合算対象になります。
●70歳以上の人の場合
同一月内の1円以上のすべての保険診療自己負担額。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※3 | |
|---|---|---|---|
| ア | 旧ただし書所得 901万円超 ※1 |
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| イ | 旧ただし書所得 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
| ウ | 旧ただし書所得 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| エ | 旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 ※2 |
35,400円 | 24,600円 |
※2 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯。
※3 過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
| 医療費負担 | 所得区分 | 外来(個人単位:一般・低所得者II・I) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者 | 現役並みIII | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 4回目以降は140,100円※2 |
|
| 現役並みII | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目以降は93,000円※2 |
|||
| 現役並みI | 80,100円+(医療費―267,000円)×1% 4回目以降は44,400円※2 |
|||
|
2割 |
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 4回目以降は44,400円※2 |
|
| 住民税非課税世帯※1 | 低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者I | 8,000円 | 15,000円 | ||
※2・・・過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
TOP
限度額適用・標準負担額減額認定証
入院した時などに「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払いが限度額までになります。(限度額を超えた分は、医療機関が国保に請求します。)
70歳以上の人については、上記の表の現役並みII・Iの人は「限度額適用認定証」、低所得者II・Iの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要になります。
※限度額は所得や年齢に応じて異なるため、上記の表にてご確認ください。
※認定証の申請手続きが間に合わず、限度額以上の支払いをされた場合には、後日、高額療養費として差額をお支払いたします。
※マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。そのため限度額適用認定証の事前申請が不要となります。
入院時の食事代
入院時の食事代は以下の表のとおりです。なお、住民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することによって入院時の食事代510円が240円等へ減額され ます。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、毎年7月末日です。これを更新するには、毎年の申請が必要です。
| 区分 | 食事の負担額 (1食当たり) |
|
|---|---|---|
| 一般・現役並み所得者 (指定難病などの方の負担額は300円) |
510円 | |
| 住民税非課税世帯(70歳以上では低所得者IIの方)※ | 過去1年間の入院日数が90日以下 | 240円 |
| 過去1年間の入院日数が90日を超える | 190円 | |
| 70歳以上で低所得者Iの方※ | 110円 | |
| 低所得者II | 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合 |
| 低所得者I | 世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、かつ収入金額から必要経費・控除を差し引いた所得金額が0円となる場合 |
申請の方法
新規に認定する場合
申請に必要なもの- 国民健康保険資格確認書等
- 身分証明書(本人または同居のご家族以外の人が申請及び受領される場合には、委任状が必要です。)
- 住民税非課税証明書(前年の1月1日以降に鹿沼市に転入した人)※申請する時期によって異なりますので、お問い合わせください。
長期該当(90日を越える入院)への変更
国民健康保険標準負担額減額認定証を持っている人で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、再度申請することによって「長期該当」になります。申請に必要なもの
- 国民健康保険標準負担額減額認定証
- 国民健康保険資格確認書等
- 長期入院が確認できるもの(病院の領収書など)
認定証の交付要件
国民健康保険税に未納がある世帯には「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。その場合はこれまでどおり、医療機関窓口で3割(義務教育就学前までは2割)を負担します。認定証の有効期限
申請月の初日から(申請月に国保加入の人は国保取得日から)7月末まで。期限後(8月以降)も引き続き認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。通常期限内に70歳になる方は、誕生月の月末まで。通常期限内に75歳になる方は、誕生日の前日まで。有効期限後も引き続き認定証が必要な場合は再度申請が必要です。
その他
診療月後に所得区分の変更(修正)が発生した場合、同一月に複数の病院に入院した場合、外来合算、多数該当の場合などは、高額療養費の再計算をして、差額支給や返納になることがあります。(申請手続きの案内が市役所から送られます。)食事代の差額の支給
標準負担額減額の要件を満たしているにもかからわらず、やむを得ず減額認定証の交付が受けられなかった場合、または減額認定証を保険医療機関に提出できなかった場合は、既に医療機関に支払った標準負担額から、標準負担額減額認定証を持っていたら支払うべき金額を控除した額について差額が支給されます。申請に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 入院時の領収書(食事負担額の内訳がわかるもの)
- 世帯主または対象者の預金口座がわかるもの(通帳など)
高額医療・高額介護合算療養費
毎年8月から翌年7月までの国保と介護保険の両方の自己負担を合算し、限度額を超えた場合に支給されます。限度額は、年齢や世帯の所得状況によって下記の表のようになります。※支給の対象となる人には、市役所から申請に関するお知らせが発送されます。
自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの世帯合算)
| 区分 | 所得要件 | 限度額 |
|---|---|---|
| ア | 旧ただし書所得901万円超 | 212万円 |
| イ | 旧ただし書所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
| ウ | 旧ただし書所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
| エ | 旧ただし書所得210万円以下 | 60万円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者III | 212万円 |
| 現役並み所得者II | 141万円 |
| 現役並み所得者I | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者I | 31万円 |
| 低所得者II | 19万円 |
申請の窓口 について
保険年金課 保険給付係
市役所 行政棟1階(窓口2番)
電話 0289-63-2166
または、各コミュニティセンターの窓口
TOP
掲載日 令和7年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2166
FAX:
0289-63-2206