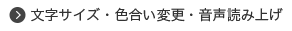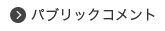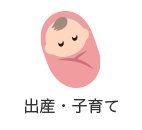後期高齢者医療制度の保険料について
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と一定の障がいがあると認定された65歳以上の人が加入する高齢者の医療保険制度で、栃木県後期高齢者医療広域連合と市が協力して運営しています。
1 保険料について
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。これまで職場の健康保険などの被扶養者で保険料を納付していなかった人も75歳になると原則として保険料を納めていただくことになります。保険料は制度を運営している栃木県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料率は、2年に一度見直されることとなっています。
保険料の算定方法について(令和6・7年度)
均等割額(45,600円)+所得割額{(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×8.84%}= 年間保険料額 (上限80万円)
- 保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額(100円未満切捨て)になります。所得割率は原則として栃木県内均一となります。
- 令和6・7年度は均等割額、所得割率、賦課限度額(保険料の上限額)が変更になりました。
| 区分 | 令和4・5年度 | 令和6・7年度 |
| 均等割額 | 43,200円 | 45,600円 |
| 所得割率 | 8.54% | 8.84% |
| 賦課限度額 | 66万円 |
80万円 |
基礎控除額は下表のとおりです。
| 前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円を超え、2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円を超え、2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円を超える | なし |
軽減措置について
所得の低い方への軽減措置
保険料「均等割額」の軽減について
世帯の所得水準によって保険料の「均等割額」が軽減されます。
その判断基準となる所得を「軽減判定所得」といいます。
軽減判定所得=同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額
※被保険者の所得に公的年金所得がある場合は、上記の金額から15万円を差し引いた(当該人の公的年金の所得金額内が限度)後の所得が軽減判定所得になります。
※世帯はその年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断されます。
| 軽減割合 | 対象となる世帯の所得 |
|---|---|
| 7割軽減 | 軽減判定所得が基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯 |
| 5割軽減 | 軽減判定所得が基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+(30.5万円×被保険者数)を超えない世帯 |
| 2割軽減 | 軽減判定所得が基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+(56万円×被保険者数)を超えない世帯 |
給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
- 給与収入額が55万円を超える者
- 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
単身世帯の場合は本人のみの所得、複数世帯の場合は本人以外にも世帯主の所得と世帯内の他の被保険者の所得の合計額によって軽減判定を行います。世帯主及び被保険者に未申告者がいる場合、軽減が受けられなくなります。
社会保険などの被扶養者だった方への軽減措置について
制度に加入した月から保険料の所得割額の負担はなく、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。
なお、所得の低い方への軽減にも該当する場合は、軽減割合の高いほうが適用されます。
2 保険料の納めかた
保険料の納めかたは、原則年金からの天引き(特別徴収)となりますが、年金天引きができない方については普通徴収(納付書またはスマートフォンアプリ(PayPay,d払い等)、口座振替)で納めていただきます。
特別徴収(年金からの天引)
対象者
年金の受給額が年間18万円以上の方が対象。(ただし介護保険料との天引き額の合計が、天引き対象となる年金の受給額の2分の1を超える場合は除く。)
納めかた
年金支給の際(年6回・偶数月)に、保険料があらかじめ年金から差引かれます。
なお、保険料は前年中の所得に基づいて算定されるので、その年度の保険料額が決定するのは7月頃になります。そのため、4月から8月は前々年中の所得によって仮に算定した保険料を納めていただき、年保険料額の決定後、差額を10月から2月の年金から納めていただきます。
4月、6月、8月(仮徴収)
前々年中の所得に基づき仮算定された保険料を天引きさせていただきます。天引き額は次のとおりです。
(1)前年度の10月以降、引き続き年金天引きが継続している場合
前年度の2月の天引き額が、各月の天引き額になります。
(2)4月から新たに年金天引きになる場合
前年度の年間保険料額(月割り減額前)の概ね6分の1が各月の天引き額になります。
(3)6月から新たに年金天引きになる場合(4月は天引きされません)
前年度の年間保険料額(月割り減額前)の概ね5分の1が各月の天引き額になります。
(4)8月から新たに年金天引きになる場合(4月、6月は天引きされません)
前年度の年間保険料額(月割り減額前)の概ね4分の1が8月の天引き額になります。
※なお、(1)又は(2)に該当する方のうち一部の方については、仮徴収額と本徴収額の差額ができるだけ均等になるよう、6月、8月の天引き額を変更させていただくことがあります。
10月、12月、2月(本徴収)
年保険料額から仮徴収の合計額を差し引いた残りを3期に分けた額。
普通徴収(納付書またはスマートフォンアプリ(PayPay,d払い等)、口座振替による納付)
対象者
年金の受給額が18万円未満の方、資格取得後間もない方や、転入された方、保険料の変更が生じた方など、年金からの天引きにならない方が対象
納めかた
納付書またはスマートフォンアプリ(PayPay,d払い等)、口座振替による納付方法があります。
令和6年12月1日から市税などの公金納付方法は、口座振替による納付が原則となりました。
「口座振替の原則化」という制度は、歳入(公金)の納期内納付を促進し、収納率の向上や行財政の安定化を図ることに加え、令和6年10月から有償となった公金取扱手数料の削減対策を強化するため創設されました。
「口座振替」は多様な納付方法の中で最も手数料が安く事務効率に優れた納付方法であり、納入義務者の皆様と協力してできる「協働による取組」ですので、まだ納付書で納付されている方は、便利で納め忘れのない「口座振替」への切り替えをお願いします。
なお、「口座振替」による納付が困難な方は、窓口納付やその他の方法で納期内に納付をお願いします。
※国民健康保険税では世帯主が納税義務者となりますが、この後期高齢者医療保険料の納付義務者は、この制度に加入する被保険者本人となりますので、口座振替を申し込む場合は、それぞれの納付義務者(被保険者)名で申し込む必要があります(振替口座は本人以外の名義の口座でも可)。
後期高齢者医療保険料のお支払い方法の変更について
「年金天引きでのお支払い」から「口座振替」に変更できます。お支払い方法の変更を希望される人は、市役所納税課(2階2番窓口)にて、下記のものをご持参のうえお手続きください。
手続きに必要なもの
後期高齢者医療被保険者証または資格確認書等、振替口座の通帳、通帳印
保険料を納めていないと
保険料の滞納が1年以上続くと、医療機関の窓口で医療費を一旦全額支払う特別療養費の支給や医療給付の差止めなどの処分の対象となります。なお、未納のお知らせとして督促状・催告書が発送される場合があります。
栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。