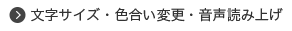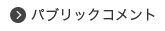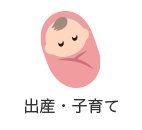自主防災会を設立しましょう
自分たちのまちは自分たちで守る
もし、私たちのまちに大災害が発生したら電話の不通、道路事情の悪化、火災の延焼などにより都市機能は分断され、市区町村や防災機関による消火活動、救出救護などの防災活動が十分に果たせなくなることが考えられます。地域には災害時要支援者となる高齢者、身体機能障がい者、介助の必要な人々もたくさん住んでいます。
平成7年1月に発生した「阪神淡路大震災」では、交通や通信機能等が混乱し、行政による救助や消防活動は著しく低下してしまいました。このため、人命救助や初期消火活動のほとんどが、家族隣人などの地域の力によって行われました。この大災害を通じて、「地域防災力」が重要であることを学びました。
「自分たちのまちは自分たちで守る」という強い意識を持って地域防災活動に取り組んでいきましょう。
自主防災会を設立しましょう
「自主防災会」とは、災害時の被害を軽減させるため住民個人を直接的間接的に支える地域における基盤組織です。
家庭における日頃の備えや、いざというときの心構えとともに、近所の人たちと協力しあい、地域の防災活動を効果的に行うための組織です。
鹿沼市では、自治会組織を活用した自主防災会の設立を促進しています。設立までには、会の規約や自主防災計画など組織作りを支援し、設立後には防災資機材の支給等を行っています。
災害に強いまちづくり、災害に強いひとづくりを目指すために自主防災会を設立しましょう。
自主防災会の設立状況
令和6年12月現在、鹿沼市の「自主防災会」は118組織あり、自治会単位でみた設立率は約96%です。
自主防災会への支援
鹿沼市では、自主防災会の組織作りのため、会の規約や自主防災計画などを作成する支援を行っています。
自主防災会が設立された後には、鹿沼市自主防災資機材等支給事業、コミュニティ助成事業(自主防災組織育成助成事業)により、防災資機材の支給等を行っています。また、出前講座や防災研修、防災訓練への参加等により自主防災会の活動への支援を行い、自主防災会のリーダーや会員の育成を図っています。

新たに設立した下粕尾自主防災会、塩山町自主防災会は、鹿沼市自主防災資機材等支給事業により、防災資機材を整備しました。
鹿沼市は地域の自主防災活動に対し、引き続き積極的な支援を行っていきます。

石橋町自主防災会、三幸町自主防災会、日吉台団地自主防災会、朝日町自主防災会、見野自主防災会、楡木開運町自主防災会、旭が丘自主防災会、入粟野自主防災会、上粕尾自主防災会は、宝くじの社会貢献広報事業である(一財)自治総合センターの令和6年度コミュニティ助成事業「地域防災組織育成助成事業」により防災資機材の整備を行いました。
自主防災会の活動
自主防災会として、いざというときにスムーズに活動するためには、日頃からの活動をどのようにしていくかが大切となります。活動内容の例は以下のとおりです。
平常時
- 防災知識の普及
- 防災訓練の実施
- 地域内の防災点検
- 防災資機材の整備
- 災害時要支援者とのかかわり
災害時
- 各班の連絡調整等
- 情報の収集伝達
- 消火器等による消火
- 住民の避難誘導
- 負傷者の救出救護
- 給食給水活動
平常時の活動
防災知識の普及
防災活動上で必要な情報を地域住民に広めていくことが大切です。防災知識を浸透させていく方法はたくさんあります。
- 学習会や講演会の開催
学習会は、住民相互の防災意識、防災知識を深めるために有効な手段です。例えば、「家庭でできる防災対策」「災害時に隣近所で助け合えること」といったテーマを設定し、みなさんで意見交換を行えば、一人では気づかなかったようなことが学べるでしょう。また、終了後にまとめを作成して記録しておけば、いつでも振り返ることができます。
講演会は、企画内容を狭い範囲に限定せず、いろいろな講演者に依頼してみましょう。市職員や消防士だけでなく、近所の医師や大工、大災害の経験者など様々な分野の方から講演していただくことで、違う視点からの防災対策が学べます。 - 広報紙の発行
広報紙は、住民に対する最も有効なPRとなります。学習会や各種訓練のように実際に出向く必要もなく、いつでも手軽に読めるものだからです。
新しく広報紙を作成しなくても、自治会の広報誌等の一部に防災に関するコーナーを設けるのも一つの手段です。
内容としては、市町村や他地域の防災関連情報も大切ですが、地域の身近な話題も取り入れて、親しみを持って読んでもらえるようにしてみるのも良いでしょう。
防災訓練の実施
防災訓練は、災害時に的確な対応をとるために欠かせないものです。訓練の種類としては、初期消火訓練、避難誘導訓練や炊き出し訓練などです。地域でのイベントに合わせて実施するなど、工夫して参加者全員が楽しみながら行えるようにするのも一つの方法です。
令和6年8月3日に実施した防災訓練(東部地区)の様子
避難訓練

避難所運営訓練

救助訓練

防災講習会
地域内の防災点検
大地震等が発生した場合、被害の発生又は拡大の原因となるものが数多くあると考えられます。日頃から、その点検を行い、さらには防災マップ等を会員みんなで作成すれば、住んでいる地域をよく知る機会を提供すると同時に、活動指針を検討したり、災害時の対応を考える重要な手がかりになります。
点検箇所の例として、以下のようなものがあります。
家庭内の点検箇所
- 消火器などの消火用品
- 灯油タンクやガスボンベの設置状態
- ガス器具や石油器具
- ブロック塀や石垣
- 屋根やアンテナ
地域内の点検箇所
- 商店の看板や自動販売機の設置状況
- 崖や河川の状態
- 交通渋滞箇所
- 路上駐車の多い場所
- 危険物を取り扱う施設の場所(工場など)
防災資機材の整備
非常時に活動する際、なくてはならないのが各種の防災資機材です。
一度に揃えることができなくても、地域の実情に応じて少しずつ整備しておきましょう。鹿沼市では設立する組織に対して、世帯数に応じた防災資機材整備の支援を行っています。
災害時要支援者とのかかわり
災害時要支援者とは
傷病者、身体障がい者、精神障がい者をはじめ、乳幼児や高齢者、外国人など自分の身に危険が差し迫った場合、それを察知する能力、危険を知らせる情報を受け取る能力、そうした危険に対して適切な行動を取る能力の面で、ハンディキャップを持つ人々を総称する概念です。
地域の援助体制を具体的に決める
地域内の災害時要支援者に対する援助体制を具体的に決めておきましょう。特に避難誘導と安否確認体制を確立しておくことが重要です。
注意すること
- 一人の災害時要支援者に対して、複数の住民で援助体制を組みましょう。
- 具体的な活動手順を決め、日頃から災害時要支援者と一緒に訓練しましょう。
災害時の活動
災害時に円滑な活動を行うためには、会員を班分けして「誰が何をするのか」を明確にしておくことが大切です。
以下は役割分担の一例ですので、地域の実情に合わせて班を編成しましょう。
災害時の活動を念頭に、平常時から準備をしておきましょう。
| 役割(班) | 災害時の活動 | 平常時の活動 |
|---|---|---|
| 各班の連絡調整等 (総務班) |
|
|
| 情報の収集伝達 (情報班) |
|
|
| 初期消火 (消火班) |
|
|
| 住民の避難誘導 (避難誘導班) |
|
|
| 負傷者の救出救護 (救出救護班) |
|
|
| 給食、給水活動 (給食給水班) |
|
|