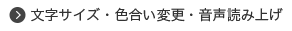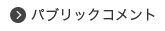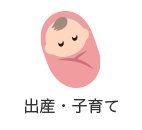みなとモデル二酸化炭素固定認証制度について
「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」について
鹿沼市では、平成24年2月に東京都港区と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」を締結し、鹿沼市の森林整備を促進し、二酸化炭素吸収量を増大させることにより、国内林業の活性化及び低炭素社会の実現を目指します。
制度の概要・ポイント
この制度では、港区と協定を締結することにより、鹿沼市内の森林から産出された木材や木材製品(協定木材)について、港区で建築を行う建築主に一定量以上の利用を促します。
制度についての詳細は、(みなと森と水ネットワーク会議みなとモデル二酸化炭素固定認証制度)をご覧ください。
既に登録された事業者もこちらからご覧になれます。
協定木材の供給に係る登録事業者募集のお知らせ
鹿沼市では、この制度を活用し木材を供給する事業者(登録事業者)を募集しています。
登録事業者の皆様には「鹿沼市みなとモデル登録事業者連絡会」の構成員として、
年1回の総会において木材の出荷・使用状況や関連イベントへの出展などの情報を共有し、
鹿沼市産木材の需要拡大に向けてご協力いただいております。
皆様の積極的な参加をお待ちしております。
登録事業者となる条件
- 以下のいずれかの条件を満たす鹿沼市内の森林より産出された木材・木材製品(「協定木材」という)をほかの木材と分別して管理、加工、出荷することが可能であること
(2) 独立した認証機関による森林認証(FCS,SGEC等)を受けており、森林法第11条の規定に基づく森林経営計画と同等の経営計画を有していること。
(3) 森林法第2条第3条に定める国有林であり、同法第7条の2の規定に基づき地位区別の森林計画がたてられている。
- 鹿沼市内に事業所(営業所含む) がある。ただし、鹿沼市内で製造される製品と競合しない場合はこの限りでない。
- 分別管理について、以下の条件を満たしていること。
(2) 入出荷、加工、保管の各段階において合法木材・協定木材と非合法木材とが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
※1 「合法性」とは:伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関する法令に照らし手続きが適切になされたものであること。
※2 「持続可能性」とは:持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
- 帳票管理について、以下の条件を満たすことができること。
(2) 関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
- 本取組みについて、責任者が1名以上選任されていること。
- 鹿沼市に提出する文書の内容が、港区のみなとモデル二酸化炭素固定認証制度HPで公開されることを承諾すること。(業態による例外あり。)
- 協定木材と他の国産材、外国産木材、非木質材料等とを混合した製品を取り扱う事業者については別途、遵守事項及び提出書類があります。
混合製品を取扱う事業者は、取扱製品情報シートを記載するとともに、次の資料を提出してください。
- 当該製品に協定木材および国産合法木材が使われていること及びその使用量を証明する書類(販売先に出す証明書類のサンプル) 【事業者登録の手引き27 ページ参照】
- 製品情報シートに記載した数値の計算根拠(所定の計算シートを作成して提出)【事業者登録の手引き28 ページ参照】
登録事業者が行う業務
- 供給可能な木材及び木材製品に関する情報提供
供給可能な木材及び木材製品の基本情報を示す一覧表を別に定める様式により申請時及び製品の変更時に、鹿沼市へ提出する。
- 協定木材の供給
 ※3「uni4m」マークとは・・・協定木材であることを示すもので、鹿沼市から登録事業者へ配布するマーク。
※3「uni4m」マークとは・・・協定木材であることを示すもので、鹿沼市から登録事業者へ配布するマーク。
実際には、市名の入ったデザインのものを登録事業者へ配布します。
(3) 2次加工以降を担う登録事業者は、半製品の受領時に「uni4m」マークの有無を確認し、「uni4m」マークがラベルされていたもの(協定木材)については、分別管理のうえ、出荷時に納品書に「uni4m」マークをラベリングする。
(4) 協定木材の供給実績を年度毎に記録し、鹿沼市へ報告する。
*報告時期は、鹿沼市から年度末にお知らせいたします。
*報告様式は以下をご利用ください。
・![]() 協定木材の取扱状況報告.xls (EXCEL 32 KB)
協定木材の取扱状況報告.xls (EXCEL 32 KB)
・![]() 伐採後の森林の更新状況報告.xls (EXCEL 34 KB)
伐採後の森林の更新状況報告.xls (EXCEL 34 KB)
登録のための提出書類
- uni4mのホームページからダウンロードしてください。
提出期限
随時、申請書の受付・登録を行います。
提出方法
持参、又は郵送でご提出ください。
紙ベースで1部と、メールによるデータの提出をお願いします。
提出先・お問合せ先
鹿沼市経済部林政課(新館5階)
電子データ送付先 rinsei@city.kanuma.tochigi.jp
*メール送付の際は、必ずお電話でその旨ご連絡願います。